かき菜(かきな)は、アブラナ科アブラナ属の野菜です。
別名を芯切菜(しんきりな)、本稿でも紹介している宮内菜、東京近郊では、「のらぼう」と呼ばれています。
かき菜は、群馬県、栃木県のうち、特に両毛地区で、古くから品種改良(群馬県農業試験場等)を経ながら、
現在もなお、さかんに栽培されている伝統野菜です。
かき菜は、「なばな」の在来種とされ、伸びてくる花茎を欠きとって収穫するのですが、
「佐野の茎立」として、古来からその記述があるほどです。
(佐野:栃木県佐野市)
このように、かき菜は、古来より両毛地区のほとんどの農家や家庭菜園で栽培されているほど、無くてはならない人気野菜です。
しかし、限られた地域で普及した野菜のためか、全国的に知られた野菜ではないかも知れません。
また、ローカルな地質などの生育条件によるものなのかはよくわかりません。
しかし、この地方で、かき菜が出回り始めると、ほうれん草の消費が落ちるほど、人気のある野菜なのです。
そんな「かき菜」の栽培方法を本記事で御覧いただくと、あなたの地域でも栽培できるかも知れません。
さらに、早春に収穫できることから、完全な無農薬で栽培可能な野菜でもあります。
ぜひ、あなたも栽培してみては、いかがでしょうか。
子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や農園芸などの環境教育活動に携わってきました。
本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。
【クイズ-1】 伝統野菜「かき菜」が登場する書物は、次のうちどれでしょう?
- 日本書紀
- 魏志倭人伝
- 古今和歌集
- 万葉集
【クイズ-2】 野菜の原産地とは次のうちどれでしょう?
- その野菜が多く消費されている地域
- その野菜のルーツとなる原酒が自生する地域
- その野菜を昔から栽培している地域
- その野菜の種が化石として発見された地域
* 正解は、最後のページを御覧ください。
目次
【かき菜の育て方・問い合わせ:苗は流通していますか?】
 収穫時を迎えたかき菜(2025.3.28)
収穫時を迎えたかき菜(2025.3.28)画像は、かき菜「宮内菜(晩生種)」です。
お寄せいただいた問い合わせの中に、「かき菜の苗はどこで売っていますか?」という御質問をうただきました。
結論から申し上げますと、かき菜は秋(9月)に種をまき、晩秋(11月)に間引きや移植して越冬させます。
そのため、苗は流通しているとすれば、苗が小さい時期(秋)でしょう。(筆者は流通しているかき菜の苗は、店頭で見たことはありません)
収穫したかき菜はしおれやすく、収穫(欠き採っって間もない)してすぐに調理を擦るのがベストです。
このような理由から、かき菜の苗や収穫したかき菜は流通させにくいと考えられます。
本記事では、「それなら、自分で新鮮で美味しいかき菜を育ててみよう!」というみなさんの御要望に、かき菜の生産地からお応えいたします。
【かき菜の育て方:秋に種をまくかき菜】
「かき菜」は、北関東「両毛地方」で育てられた野菜です。
「かき菜」の品種は、複数あります。
以下に示す「宮内菜」よりも、早く収穫できます。
筆者の住む地方では、「かき菜」は欠かせない野菜です。
そのため、筆者は、早生種と晩成種というように、2種類の品種を組み合わせて栽培し、
長く収穫できるように工夫しています。
[品種名]:かき菜 栄養と風味ある「とう菜」
トーホクのタネ 品種番号 05080
[科・属名]:アブラナ科 アブラナ属
[原産地] :両毛地域 伝統野菜
[生産地] :アメリカ
特 性
- 両毛地方で育てられた「とう」を食べる「かき菜」です。
- 翌春の3~4月に収穫し、やわらかく風味があります。
- 早春の両毛地方に、なくてはならない野菜です。
| まき時:暖かい地域 | 8月下旬~ 11月上旬 |
|---|---|
| :寒い地域 | 8中旬~ 11月上旬 |
| 収穫の目安 | 翌春3~4月 |
| 収穫部位 | とう |
| 数量 | 10ml |
| 発芽率 | 90%以上 |
| 発芽適温(地温) | 20~25℃ |
| 生育適温 | 10~20℃ |
【かき菜の仲間:宮内菜】
「宮内菜」は、北関東「両毛地方」で育てられた野菜です。
「かき菜」の種類に属します。
[品種名] :あぶら菜「宮内菜」
香り・再生力抜群 収量の多い「かき菜」
カネコ種苗株式会社
[科・属名]:アブラナ科 アブラナ属
[原産地] :両毛地域 伝統野菜
[生産地] :イタリア
特 性
葉色は淡緑色で、浅い切れ込みがあり、内側にわん曲して葉柄は長いです。
葉は、やや厚く柔らかいです。食味は甘みに富み、だれもが好む香りもあります。
再生力が非常に旺盛で、第1側枝で30本、第2側枝で65本前後となり、
他の芯摘油菜に比べ、約3週間程度、収穫期に幅があります。
特に、晩生多収品種です。
| まき時:暖かい地域 | 9月上旬~ 10月下旬 |
|---|---|
| :寒い地域 | 8中旬~ 9月中旬 |
| 収穫の目安 翌春 |
中・暖地:3~5月 冷涼地:4~6月 |
| 収穫部位 | とう |
| 数量 | 10ml |
| 発芽率 | 85%以上 |
| 発芽適温(地温) | 15~20℃ |
| 生育適温 | 15~20℃ |
[品種名] :宮内菜(芯摘菜)
✩再生力旺盛な「かき菜」晩生多収品種!
カネコ種苗株式会社
[生産地] :イタリア
特 性
上記「宮内菜」と同じ。
| まき時:中間地・暖地 | 9月上旬~ 10月下旬 |
|---|---|
| :冷涼地 | 8中旬~ 9月中旬 |
| 収穫の目安 翌春 |
中・暖地:3~5月 冷涼地:4~6月 |
| 数量 | 10ml |
| 発芽率 | 85%以上 |
【かき菜の育て方:栽培場所の選定】
日当たり、排水、通風のよい環境を好みます。
種まきは、ポット栽培と、直まき栽培があります。
本稿では、直まき栽培を御紹介します。
【かき菜の育て方:栽培場所の準備】
種まき2週間前 苦土石灰:100~150g(約2~3振り)
種まき1週間前
堆肥:3kg 化成肥料:100g(約2振り)
* 全面に散布し、よく耕します。
【かき菜の育て方:種まき】
 ウネづくり
ウネづくり約1mのウネをつくります。
たこ糸を張って、クワなどを使い柵をきります。
 種のまき溝の
種のまき溝の約25cm間隔で、種のまき溝をつくります。
目印のたこ糸に沿って板を滑らせ、約1cmの深さの溝をつくりましょう。
種のまき溝の底面が平らで、種の上にかけた土の表面も平らにすると、発芽をそろえることができます。

 種まき(2022.9.22)
種まき(2022.9.22)今年は、高温の日々が続き、目安としていた25℃(最高気温)以下には、なかなかなりませんでした。
また、台風の影響もあり、昨年(9月12日)よりも、10日ほど遅い種まきになりました。
 板を滑らせてつくった種のまき溝(9月12日)
板を滑らせてつくった種のまき溝(9月12日)かき菜と宮内菜(かき菜の一種)の種をまきました。
ウネ幅によって、板の幅を選びます。
今回は、ウネに直まきして、移植する方法を御紹介します。
 かけた土を板で押さえる
かけた土を板で押さえる種をまいて、種が見えなくなる程度に土をかけます。
次に、かけた土の上を板でかるく押せましょう。
● 土の表面の乾燥が、ある程度緩和される。
● まいた種と土を密着させる。
● 発芽が均等にそろう。
 発芽した「かき菜」(9月23日)
発芽した「かき菜」(9月23日)【かき菜の育て方:中耕・追肥・土寄せ】
 発芽したかき菜
発芽したかき菜発芽したかき菜の周辺の土固く固くヒビ割れています。
 中耕したかき菜
中耕したかき菜かたくなった条間の土をスコップでほぐします。
特に、化成肥料のみが施され、有機質の乏しい土壌は、土の表面がかたくなりがちです。
土の表面がかたくなると、降った雨が流れ去り、土中に供給されません。
また、根に充分な空気も行き届かず、結果として吸肥作用に影響を及ぼします。
もちろん、根の周りのバクテリアや、微生物への関係にも関係してきます。(詳細は、追々お話させていただきます)
 中耕して施肥したかき菜
中耕して施肥したかき菜
 株間を中耕:かき菜(9月28日)
株間を中耕:かき菜(9月28日)晴れたり、雨が降ったりと、天気の移り変わりによって、土の表面が、次第にかたくなってきます。
中耕作業を済ませたら、有機化成肥料を与え、土とよく混ぜます。
 中耕と土寄せをしたかき菜(2022.10.5)
中耕と土寄せをしたかき菜(2022.10.5)1回目の中耕の後、条間の表面に堆肥をまきました。
1周間ほど経過しましたが、堆肥を施した条間は、さほどかたくなっていません。
2回目の中耕も、条間の土をほぐしながら、発芽した小さな苗を両側から挟むようにして土寄せします。
土寄せする前に、少量の化成肥料をまいて、寄せる土に混ぜると肥効性がいっそう高まります。
 かき菜(2022.10.8)
かき菜(2022.10.8)速効性肥料と緩効性肥料、無機肥料と有機肥料、土壌改良材と肥料との区別、などを念頭において、使い分けましょう。
詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー! 1【農園芸資料】⑹<土壌改良材と肥料>を御覧ください。
 生長する「かき菜」の苗(2022.10.16)
生長する「かき菜」の苗(2022.10.16)追肥と土寄せの効果で、だんだんと苗の生長が促進されてきました。
まばらなところもありますが、十分に苗が生長したころ他の場所に移植しますので、心配ありません。
今年(2022)は種まき時期が遅かったせいか、昨年に比べて小さいです。
 苗が倒れぎみになってきたかき菜
苗が倒れぎみになってきたかき菜
 間引きした後、土寄せしたかき菜
間引きした後、土寄せしたかき菜この段階の苗は、適宜に土寄せを行い、苗の倒状を避けるとともに、苗への肥効性を高めることが大切なポイントとなります。
 生長するかき菜の苗(2022.10.21)
生長するかき菜の苗(2022.10.21)
 虫も大好きな「かき菜」(10月6日)
虫も大好きな「かき菜」(10月6日)(注:西暦がない月日のみの画像は、昨年度です)

ずいぶん窮屈になってきましたね。
後日、成長の良い苗を別の場所へ移植します。
 かき菜(10月17日)
かき菜(10月17日)10月下旬ころ、大きな苗を別の場所に移植する予定です。
小さな苗は、お浸しにして食べましょうね。
 かき菜(10月30日)
かき菜(10月30日)植え替えの時期を迎えています。
 植え替え前の「かき菜」2022.11.3
植え替え前の「かき菜」2022.11.3
 中央:間引き前の「かき菜:宮内菜」 2023.11.1
中央:間引き前の「かき菜:宮内菜」 2023.11.1苗が豊富にある場合は、間引きして残した苗を移植せずに、そのまま育てると大株になり、
その後の生育が良い場合もあります。
かき菜の品種、作業時期、移植場所によって、結果が異なることもあります。
家庭菜園の楽しみの一つとして、いろいろ試してみましょう。
また、間引き苗は、おひたしにするとシャキッとした食感が味わえますので、ぜひ御堪能くださいね。
【かき菜の育て方:苗の移植】
 移植作業を終えた「かき菜」(10月31日)
移植作業を終えた「かき菜」(10月31日)右側一列が「かき菜」で、左側の列は「宮内菜」です。
植え替えは、霜が降りる前に済ませておきましょう。
1 ウネ幅60~70cm、株間20~40cmの間隔で定植します。
2 定植位置をクワで植え溝を掘って、水を満たします。
3 かき菜の苗は、根回りに比べて背が高いため、寝かせて定植します。
4 根もとに土を寄せます。
* 植え溝の代わりに、「球根植え器」で穴を開け、水を満たし、寝かせて植えてもいいでしょう。(植え穴に、液体肥料や活力液の希釈水を注ぐ場合、無駄がありません)
 ウネ立て作業
ウネ立て作業幅70cmのウネを立てました。
 等間隔に開けた定植する穴
等間隔に開けた定植する穴ウネの中央に、20cm間隔で植え穴を掘ります。
植え穴は、球根植え器を使うと便利です。
 水を注いだ植え穴
水を注いだ植え穴苗の活着(根張り)を促すために、活力液(HB-101など)と液体肥料を希釈(1,000倍)した水を植え穴に注ぎます。
 定植を終えた「かき菜」の苗(2022.11.4)
定植を終えた「かき菜」の苗(2022.11.4)
 かき菜の間引き苗
かき菜の間引き苗小さめの苗は根を取り除いて、お浸しなどにすると美味しくいただけます。
記事内の西暦を付していない月日のみの画像は、2021年のものです。

定植後、葉を起し始めた苗(11月5日)定植後、数日すると、葉が立ってきます。
今後、寒い冬を迎えますが、新芽がたくましく越冬し、来春、暖かくなるにつれ、大きく育ってきます。
初期生育は「宮内菜」に比べ、「かき菜」のほうがはやく、それだけ、来春の収穫も「宮内菜」よりも、はやくなります。
「かき菜」は、品種にもよりますが、中心のトウ立ち芽が太くて充実しています。
しかし、中心のトウ立ち芽を収穫した後は、「宮内菜」のほうが、脇芽の太さと収穫本数が勝っています。
2種類の「かき菜」(宮内菜も〝かき菜〟です)を育てることで、収穫期間をできるだけ長く保ち、おいしい「かき菜」を長く楽しむ工夫をしています。
それほど、ここ両毛地区では、「かき菜」を好んで栽培しています。
 種まき後、間引きのみのかき菜:2024.11.7
種まき後、間引きのみのかき菜:2024.11.7* 草丈:約50cm
種まき後、移植せずに間引き苗を食べながら、苗の間隔をだんだんと広げ、最終的には株間20cmの1本立ちとします。
一般に、大株仕立てにする場合は移植しますが、移植の時期が遅れると、その後の生育は良くありません。
また、せっかく移植したのに、葉が食害されることもあります。
そこで、栽培方法の一例として、移植せずに間引きのみで栽培する方法もあり、必要に応じて間引き苗を食用にします。(春先の本格的な収穫期前から、かき菜が長期に味わえます)
間引き苗の特徴は、シャキシャキ感のあるさっぱりとした食感が楽しめることです。
 活着した「かき菜」(11月22日)
活着した「かき菜」(11月22日)しっかり根付いて、葉をもち上げた「かき菜」です。
初霜が降りる前に、根張りをさせておくことが、ポイントになります。
 かき菜(宮内菜)2023.11.29
かき菜(宮内菜)2023.11.29直まきし、移植せずに(間引きして)そのまま育てた宮内菜です。
草丈は、すでに55cmほどに生長しています。
 順調に育つかき菜(宮内菜):2024.11.16
順調に育つかき菜(宮内菜):2024.11.16この状態で、霜が降りても元気に育ちます。
まだ、株間が密なところは随時、間引きをしておひたしなどでいただきます。
 1月のかき菜(2024.1.1)
1月のかき菜(2024.1.1)直まきした「かき菜」は。移植した「かき菜」に比べ、生長が旺盛です。
【かき菜の育て方:土寄せ・追肥 ①】
 追肥と土寄せ(2022.11.25)
追肥と土寄せ(2022.11.25)ウネの肩の部分に化成肥料を少量追肥します。(NPK=888 約40g/㎡)
追肥後に、クワなどでウネ間の土を株元へ寄せます。
追肥と土寄せを行うことで、株を丈夫に育て冬に備えます。
かき菜は、外側の大きな葉が枯れてしまっても、中心の芽がしっかり残っていれば心配ありません。
 大きさが異なるかき菜(2022.12.16)
大きさが異なるかき菜(2022.12.16)いちばん大きく育っているのは移植をしないで、小さい苗を間引いたウネの「かき菜」です。
そして、大きさを揃えて移植したウネによって、苗の大きさが異なっていますね。
結果的にトウ立ちする時期が、少しずつズレてきますから、長く収穫することができることになります。
そうです、かき菜は「トウをかき採る菜」でしたね。
 霜柱の畑で元気に育つ「かき菜」
霜柱の畑で元気に育つ「かき菜」12月20日の朝、畑に霜柱が立っていました。
それでも、元気に育っています。
 越冬中の「かき菜」(2023.1.20)
越冬中の「かき菜」(2023.1.20)冬季の作業は、ほとんどありません。
必要に応じて、株元に土寄せをしてやる程度で十分です。
<かき菜の生長による冬の作業>
 かき菜:冬の追肥作業:2024.1.8
かき菜:冬の追肥作業:2024.1.8冬の作業は、ほとんどありませんが、移植した苗と、間引きだけして直まきで育った苗とでは、当然、草丈や株の張り方に差が生じます。
上の写真は、直まきで育った株で、移植していない分、株が大きくなり過ぎています。
よく見ると、どことなく葉の色が薄くなってきました。
そこで、株元に少量の鶏フンを施しました。
野菜の葉色:ネギの穂先が緑から黄緑になるなど、肥料が不足してくると、野菜の葉色が変化します。
反対に、肥料過多の場合は、葉色が濃くなったり、葉の形状が変化したりと、いろいろな症状を示します。
不断からよく観察し、野菜とのコミュニケーションを大切にします。
【かき菜の育て方:土寄せ・追肥 ②】
 かき菜の株元の土寄せ(3月上旬)
かき菜の株元の土寄せ(3月上旬)秋に植え替えた時の外葉は、すでに枯れています。
しかし、中心の芽は、気温の上昇とともに、元気よく育ってきます。
3月上旬に、かき菜の株元へ土寄せ兼ねて、配合肥料を施し、肥効性を高めます。
筆者は、米ぬかに水を加えて腐熟させた液肥を希釈して、株元に施しています。
● ゴミバケツの3分の1ほど米ぬかを入れ、バケツいっぱいに水を入 れます。● ひしゃくなどを使って、よくかき混ぜます。
● ふたをして、腐熟させます。
* 米ぬか液肥は、冬季に作らないと、
腐熟せず、いわゆる腐敗してしまい、
強烈な悪臭を伴いますので、御注意くださいね。
【かき菜の育て方:摘芯】
 かき菜の中心の茎を摘芯(3月中旬)
かき菜の中心の茎を摘芯(3月中旬)かき菜の中心の茎を摘芯します。
かき菜は、摘芯することで、脇芽の伸長を促します。
摘芯した中央の茎は、特に柔らかく、たいへん美味しくいただけます。
 摘心した中央の茎
摘心した中央の茎かき菜は、中心部の茎を伸ばしすぎると、後に出てくる脇芽が細くて短くなり、
太くて充実した花茎が収穫できません。
中央部の茎を摘芯すると、脇芽が伸長しはじめます。
今後は、この脇芽(とう)を欠き採って収穫していきます。
<かき菜の摘心:ポイント>
 収穫したかき菜
収穫したかき菜かき菜を初めて栽培するときに、迷ってしまうのは「どの部分から摘心したらいいか」
ですよね。
中心の茎を摘心した下部から、脇芽がたくさん出てきます。
画像を御覧いただく御理解いtだけると思いますが、収穫した脇芽は、いずれも2本以上の束になっていますね。
 かき菜の摘心:悪い例
かき菜の摘心:悪い例誤って葉を採らずに、必ず分けつした下部から、欠き採るようにしましょう。
ただし、慣れないとよくわかりませんよね。
 欠き採る部分を示したかき菜の摘心位置
欠き採る部分を示したかき菜の摘心位置かき菜は、葉が混み合ってくると、上から見ただけでは摘心する位置がわかりません。
そこで、画像のように株をかき分けてみると、欠き採る部分が分かりやすくなります。
画像で記した、黒色のヒモの部分を欠き採ります。
 かき菜の分けつ位置から摘心
かき菜の分けつ位置から摘心よく見ると、ほどよく伸びた脇芽を見つけることができます。
 収穫したかき菜
収穫したかき菜
 摘心部分
摘心部分慣れてくると、かき菜の株に両手を差し入れて、摘心すべき部分を手探りできるようになってきます。

摘心部分は、つまんで軽く横に倒すだけで
ポキッと折れますので、この感覚を覚えるようにしましょう。(摘心する穂の表面は、外葉に比べてなめらかです)
反対に、簡単に折れないところは、太くなった外葉だったり、摘心すべき位置でなかったりする部分です。
<摘心:Sさんのコメントにお答えします>
 かき菜:2023.2.27現在(栃木県足利市)
かき菜:2023.2.27現在(栃木県足利市)コメント欄に、簡単な原因と対処について
返信させていただきました。
本記事では、説明が十分でなかったことをお詫びします。
Sさん、ありがとうございました。
これから、かき菜の摘心について追記いたしますので、よろしかったら御覧ください。
まず、上部の画像を御覧ください。
画像左側のかき菜は、種まきして移植せず、同じ場所で、間引きして栽培した列です。
そして、2列目~からは、苗床から1本ずつ移植して栽培してきました。
 かき菜:大きい苗(2023.2.27)
かき菜:大きい苗(2023.2.27)種をまいて間引きし、植えかえなかった苗は、草丈が50cm程度になっています。
 かき菜:小さい苗(2023.2.27)
かき菜:小さい苗(2023.2.27)それに比べ、1本ずつ移植した苗は、苗床から移植したため、生長が抑制され、移植せずそのまま栽培した苗よりも小さく、草丈は15cm程度です。
昨年は、移植した苗を3月中旬に摘心しています。
したがって、現在(2月下旬)、移植した苗は小さくてまだ摘心できません。
 かき菜:大きい苗(2023.2.27)
かき菜:大きい苗(2023.2.27)それでは、移植せず間引きだけで栽培してきた大きい苗の摘心をしてみましょう。
これくらいになれば、摘心に十分耐えられる大きさになっており、脇芽を伸すだけの体力が備わっています。
 かき菜:摘心(2023.2.27)
かき菜:摘心(2023.2.27)かき菜の株元をかき分けて、中心の茎を探します。
そして、包丁を使い茎もとをカットします。
間引きのみで栽培すると、どうしても株間が狭くなりがちになり株間が混雑してしまいます。
その点、移植栽培は初期生長はゆっくりですが、3月からの生長は、むしろ間引きのみの株よりも順調に生長していきます。
しかし、移植する時期が遅れたり、移植場所によって、間引きのみで栽培した株よりも生長が劣ってしまう場合もあります。
自分の庭や畑に合う方法をいろいろ試してみるのも楽しいですね。
 かき菜:摘心した茎(2023.2.27)
かき菜:摘心した茎(2023.2.27)茎をカット(摘心)する部位は、茎が枝分かれする下です。
そのため、摘心した茎は各枝がバラバラにならず、2~3本の束になっています。
 かき菜:摘心した株(2023.2.27)
かき菜:摘心した株(2023.2.27)中央主軸の茎がカットされると、これより下の茎が次第に伸びてきます。
 かき菜:摘心した茎(2023.2.27)
かき菜:摘心した茎(2023.2.27)30cmほどに生長した中心の茎ですが、茎が束になるようにカットされていますね。
このようにカットすると、茹でやすくて調理も楽です。
やがて出てくる脇芽も、同じように束の状態で収穫していきます。(束の下部:簡単に折れる部分があります)
 収穫したかき菜(2023.2.27)
収穫したかき菜(2023.2.27)収穫した中心の茎は、特に柔らかく甘味もあってもっとも美味しい部分です。
 かき菜:2025.3..11
かき菜:2025.3..112025年3月のかき菜です。
 摘みとったかき菜:2025.331
摘みとったかき菜:2025.331
 摘みとったかき菜:2025.331
摘みとったかき菜:2025.331北関東では3月になると、今まで活躍してきたホウレン草は、かき菜の人気に負けてしまうほどです。
 収穫したほうれん草(2023.2.27)
収穫したほうれん草(2023.2.27)ホウレン草も、今までお疲れ様でした。
 かき菜:追肥と中耕作業
かき菜:追肥と中耕作業摘心下後は、化成肥料(8:8:8)を40g/㎡(かるくひと握り)を施し、中耕をかねながら、
株元に土寄せしておきましょう。
こうすることで、次に出てくる脇芽の生長を促します。
なお、現在、化成肥料が高騰していますので、土壌改良も兼ねて、米ぬか水肥、鶏糞などの有機肥料と組み合わせて施肥することをおすすめします。
かき菜の中央摘心のタイミングは、株の大きさによって異なります。
早過ぎると、株が充実できず脇芽の生長が不十分に、また、遅過ぎても脇芽が細くなり、ツボミがつきやすくなります。
 収穫前のかき菜
収穫前のかき菜中央摘心を終えた後、側枝が十分に生長しました。
 かき菜:2023.3.22
かき菜:2023.3.22移植をしたかき菜(前方)も、中心の茎が欠き採れるようになり、摘心を済ませました。
今後、どんどん脇芽が出てきますので、収穫の遅れに注意し、摘心はなるべく低い位置で行いましょう。
 かき菜の株立ち:2024.3.16
かき菜の株立ち:2024.3.16すでに3回ほど収穫を済ませた、かき菜ですが、草丈は約70cmほどに育っています。
(目安の角材の長さ:70cm)
改めて、わかりずらい「かき菜の収穫方法(側芽とり)」の具体例を復習しておきましょう。
 側芽を収穫したかき菜:2024.3.16
側芽を収穫したかき菜:2024.3.16収穫した側芽(側枝)の根元を拡大して見ると、
 収穫したかき菜の根元
収穫したかき菜の根元収穫した脇芽は、すべて束になっていますね。
葉は単独ではなく、枝分かれする位置の下部をポキッと、かき採ってくださいね。
 収穫したかき菜:4回目の収穫
収穫したかき菜:4回目の収穫しかし、生長にともなって摘心位置はおのずと高い位置になり、やがて、細い脇芽しか収穫できなくなってきます。(側芽の先端に、ツボミが出てきますが食べられます)
 だんだんと細く硬くなってきたかき菜
だんだんと細く硬くなってきたかき菜

4月の中旬近くなると、脇芽も次第に細くなってきます。
また、収穫した脇芽の下部が特に硬くなってきますので、欠き採った後、少し下部を切り取ってから茹でるといいでしょう。
脇芽が極端に細くなってくると収穫は終了に近づきます。
 収穫末期のかき菜(2023.4.17)
収穫末期のかき菜(2023.4.17)
 かき菜のツボミ(2024.4.15)
かき菜のツボミ(2024.4.15)2024年4月15日現在では、かき菜のツボミが出てきたものの、収穫はまだ続いています。
品種は「宮内菜」ですが、種まき後、移植せず「間引き栽培」のほうが株も充実して(冬季の追肥の効果がある)長い間、収穫できる傾向にあるようです。
 かき菜の花(4月上旬)
かき菜の花(4月上旬))
 かき菜の花
かき菜の花<菜の花を楽しみながら、かき菜を収穫しましょう>
 菜の花を楽しみながらの収穫
菜の花を楽しみながらの収穫穂が細くなってきた株は、そのまま花を咲かせて観賞用とします。
上の画像の手前側の株は、まだ太い穂が出ていますので収穫して利用します。
今まで、たくさん収穫してきましたので、これからは、菜の花を楽しみましょうね。
クイズ-1 正解:万葉集
* 万葉集の東歌に歌われた「茎立」(かき菜)。
クイズ-2 正解:その野菜のルーツとなる原酒が自生している地域
最後まで御覧いただき、ありがとうございました。
本記事に限らず、御質問などがございましたら、お気軽にコメントをお寄せください。
(ニックネームのみでも送信可能です)






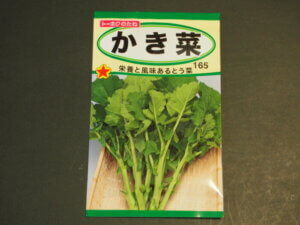
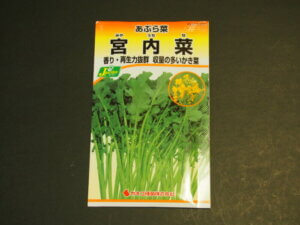
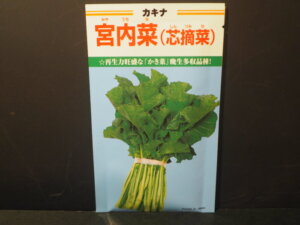




















大変参考になりました。
質問です
中心の茎を摘芯しました。
そうしましたら、かきなは伸びてこないのに花芽がたくさん出でしまいました。
なぜですか?
S-様、ご質問ありがとうございます。
「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき菜は伸びてこないのに
花芽がたくさん・・・」
まず、一番に考えられる原因は、中心の芽を摘心した位置が
高すぎた(株元から上に離れ過ぎた)ためでしょう。
かき菜は、思い切って中心の茎をできるだけ株元近くから摘心します。
「かき菜」の品種によって、トウ立ちする特性が異なりますが、
脇芽(脇枝)を収穫していくのですが、かき菜の生長とともに、
収穫する脇芽の位置が株元より、だんだん上部になってきます。
このように、収穫を続けていくと、地表から高い位置に出る脇芽は
次第に細くなり、花芽もつきやすくなってきます。
現在の対処法としては、株元の外葉を数枚残して、
中心を再び切り戻す(1回目の摘心部分より低い位置で)
といいでしょう。
そして、摘心の後は、化成肥料を追肥し、
株元に土寄せしておきましょう。
説明が十分でなかったことをお詫びいたします。
さっそく、「摘心の方法」について、
記事本文にて補足・追記いたしますので、
御覧いただけたら幸いです。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。